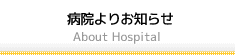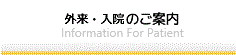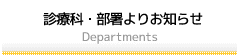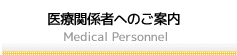ホーム > 診療科・部署よりお知らせ > 研究検査科

研究検査科
臨床検査の重要性
研究検査科では、血液や尿に代表される体液に含まれる様々な成分の分析を行う検体検査、感染症の原因となる細菌やウイルスの検査を行う微生物検査、心電図・脳波・呼吸機能・超音波検査などを行う生理機能検査などを実施しています。科学的根拠に基づいた客観性の高い検査データを提供することにより、病気の早期発見や診断治療、経過観察に貢献しています。当院では、これら診療に欠かすことができない検査を、医師1名と臨床検査技師5名が担当しています。
主な検査項目の分類
I. 血液・凝固検査
- 血液中に含まれる赤血球・白血球・血小板の量や形態を検査します。また、血液の固まりやすさについて検査します。
II. 生化学検査
- 主に血液中に含まれる蛋白質・酵素・糖質・脂質・ホルモンなどの成分を分析します。臓器の機能と密接に関連する成分があります。
- 肝機能検査
・ビリルビン、γ-GTP、AST、ALT、ALP、コリンエステラーゼ - 腎機能検査
・クレアチニン、シスタチンC、尿素窒素、ナトリウム、カリウム、クロール、β2-ミクログロブリン - 糖質代謝
・血糖、グリコヘモグロビンA1c - 脂質代謝
・LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪、総コレステロール
III. 尿検査
- 尿の成分を調べることにより、体内の様々な兆候を知ることができます。簡単に採取でき、分析も比較的速いというメリットがあります。
IV. 微生物検査
- 血液・尿・便・喀痰などに存在する微生物を培養し、同定を行います。また、その微生物にどのような薬剤が効くのか検査し判定をします。
V. 免疫血清検査
- 抗原抗体反応を用いて感染症の有無やホルモンを検査します。代表的なものに新型コロナウイルスやインフルエンザウイルス、肝炎ウイルスなどがあります。
VI. 生理機能検査
- 心電図検査(安静心電図、ホルター心電図)、超音波検査、脳波検査、誘発筋電図検査、呼吸機能検査、聴力検査など、体から直接記録を行い、様々な機能を調べます。
VII. 病理検査
- 細胞診検査、組織診検査
・喀痰や尿に含まれている細胞、皮膚、胃・大腸などの粘膜、内臓器から採取された細胞や組織を、顕微鏡で観察して調べ、腫瘍の診断や病気の原因を推定します。 - 病理解剖
・残念ながら病気で亡くなられた患者様については、ご遺族の同意を得た上で病理解剖を行うことがあります。解剖によって、内臓器、脳脊髄、筋神経などを調べ、死因や病態、病気の広がりを明らかにします。また現在治療法のない神経難病などにおいては、病理解剖の際に採取された組織が、今後の医学の発展、次世代の患者となる人たちの役に立つ研究につながる可能性もあります。解剖に際しては患者様の尊厳を保ち、終了後は清浄した上でご遺族の元にお返し致します。